学級活動とか道徳とか授業とかで結構5分ぐらい時間が余るようなことありませんかそんな時に5分位で話せるちょっとした小話があると非常に便利です。
私自身、よく授業とか学級活動とかの余剰時間にこの話をしています。今回はその中でも定期考査前とか学力テスト前なんかに使いやすいネタとしてダイニングクルーガー効果のお話を紹介します。この記事を読んで、このダニングクルーガー効果のお話を覚えると、ちょっと余った時間に児童生徒に一生使える心理効果のお話をすることができます。よければぜひお使いください。
ダニングクルーガー効果とは?
ダニングクルーガー効果と言うのは、「能力が高い人の能力が高いゆえに、自分の能力を低く見積もってしまい、能力が低い人ほど能力が低いゆえに、自分の能力を高く見積もってしまう心理効果の事」だと私は解釈をしています。
例えば、能力が高い人ほど「私なんてまだまだ」と自分を低く評価し、能力が低い人ほど「自分は良くできる」と自分を高く評価してしまうようなシーンに出くわした事はありませんか?
これがまさにダニングクルーガー効果です。
私自身、仕事柄、多くの成績上位層の子供が不安で押しつぶされそうになるのを見てきましたし、多くの成績下位層の子供が自信たっぷりにテストに対策なしで挑んでくる様子を見てきました。
ですから、テスト前なんかの余った時間にお話をしてきました。
私がダニングクルーガー効果について知ったのは、「バカと無知」(橘玲 著)と言う本でした。その詳しい実験内容などはそちらに譲るとして、この記事ではこのダニングクルーガー効果を知っておくことのメリットや使い所なんかをお伝えしていこうと思います。
ダニング・クルーガー効果を伝えるメリット:励ましと牽制が同時にできる
このダニングクルーガー効果のお話をする1番のメリットは、成績上位層の不安を抱えがちな子供に対して励ますことができ、同時に成績下位層の自信過剰な子供に対して牽制することができる点です。
というのも、どちらの子供にも、「自分の能力を正しく見積もれているか?」と問いかけることができるからです。
成績上位層の子供には「あなたは今のままで大丈夫だよ。油断しないようにね。」というメッセージになりますし、成績下位層の子供には「自信満々だけど、本当に大丈夫?」と言うメッセージになります。
ダニングクルーガー効果の話の使いどころ
特に定期考査とか、テストの前なんかにこの話をすると、冒頭にも紹介したように成績上位層の子供にも、成績下位層の子供にも「今の自分は本当に大丈夫か?」と自問自答する機会を与えることができます。実際私もこの話をしていると、普段話を聞かないような子供もちょっと熱心に話を聞くような様子を見る瞬間がかなり多かったと感じています。
この記事を書いている現在、9月の中旬です。ちょうど中間考査とか実力テストがある時期ですので、使い所としてはちょうど良いのではないでしょうか。
まとめ
ダニングクルーガー効果と言う人間の心理効果についてのお話を記事にしました。
- ダニングクルーガー効果とは、能力が高い人の能力が高いゆえに、自分の能力を低く見積もってしまい、能力が低い人ほど能力が低いゆえに、自分の能力を高く見積もってしまう心理効果の事
- この話をすることで成績上位層の子供には励ましのメッセージ、成績下位層の子供には牽制のメッセージになる
- テスト前といった本番前に使いやすい
このような話が5分程度でできるので紹介しました。より詳しく知りたい方は私がこの話を知った元ネタの「バカと無知」(橘玲 著)を読むことをおすすめします。
それでは、明日も良い1日を!
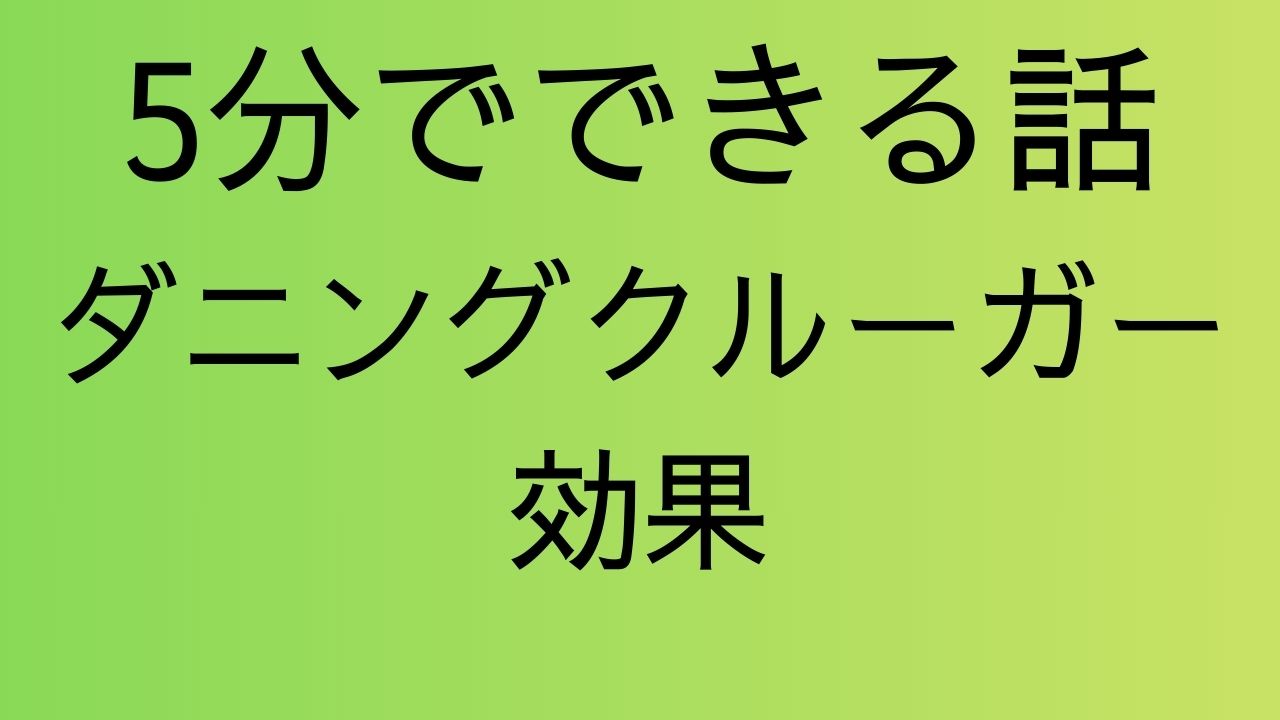


コメント