今回はかなりニッチな話です。中学校国語科の先生向けのお話です。
私の勤めてきた自治体では、光村図書の国語教科書が採用されていました。
説明的な文章を題材として扱う際、教科書では「序論・本論・結論で構成される」とされています。
問題は、この序論・本論・結論の見分け方です。これを中学生にもわかりやすく伝えて、なるべく他の題材でも扱えるように説明するにはどうしたらいいか?と試行錯誤してきました。
結論:文章の最初と最後を見よ
先に結論から書きます。文章の最初と最後を見ると序論・本論・結論を見分けやすいです。
理由:最初の話題に最後に戻ってきがちだから。
なぜなら、説明的な文章の構成は
- 序論:話題提示
- 本論:具体的な説明(問いと答え、例示)
- 結論:まとめ、筆者の主張
と教科書ではされているためです。
特に結論で筆者の主張がされている題材などは顕著で、序論で主張に関わるワードを出して、結論でまた主張につながる話題に帰ってきがちです。
例えば:動物は4本足である話
こんな説明的文章があるとします。
- 序論:動物は何本足か?
- 本論1:犬は4本足である。
- 本論2:猫は4本足である。
- 本論3:カメは4本足である。
- 結論:このように、動物は4本足である。
この例ですと、最初(序論)と最後(結論)に「動物」というワードが共通します。
このように例を出してから、「さあ、この説明的な文章を序論・本論・結論に分けてみましょう」
と指示を出すと割と活動に取り組みやすいです。どこを見たら良いかがわかりやすいためです。
プラスα:題名もヒントに出すと効果が上がる
とはいえ、中には光村図書の「ちょっと立ち止まって」のように、
- 序論:別の見方で見え方が変わったことはないか?
- 本論1:ルビンのつぼ
- 本論2:おばあさんと女性
- 本論3:ドクロと女性
- 結論:ちょっと立ち止まって見方を変えてみてはどうか?
といった説明的な文章もあります。
そんな時には題名をヒントにすると効果があります。「題名も見て序論・本論・結論を分けてみましょう」と声かけをすると、控え目に見て半分以上の中学生が序論・本論・結論の仕分けができるようになりました。
途中でちょいちょい話し合わせて進めていくと、全体では仕分けができます。
使い所はモアイ像
この話の一番の使い所は2年生で扱う「モアイは語る 地球の未来」という題材です。
ぜひ動物の話と題名のヒントを織り交ぜて序論・本論・結論を分けさせてみてください。
面白いくらい段々と正解に辿り着きます。
まとめ
中学校の国語の先生向けに、説明的な文章の序論・本論・結論の見分け方を紹介しました。
- ポイントは、文章の最初と最後を見よ。
- なぜなら、最初の話題に最後に帰ってくるから。
- 例えば、動物は4本足の話では動物の足の本数の話題に帰ってくる。
- 題名もヒントに使えば、効果が高くなる。
という話です。
教科書にもちゃんと説明的文章の読み方的なページはあるのですが、「最初と最後に共通のワードがある」といった助言はありません。
ここは現場の先生の助力が必要なところではないかと個人的には思っています。
最後までお読みくださりありがとうございます。
この記事がお役に立てば幸いです。
それでは明日も良い1日をお過ごしください。
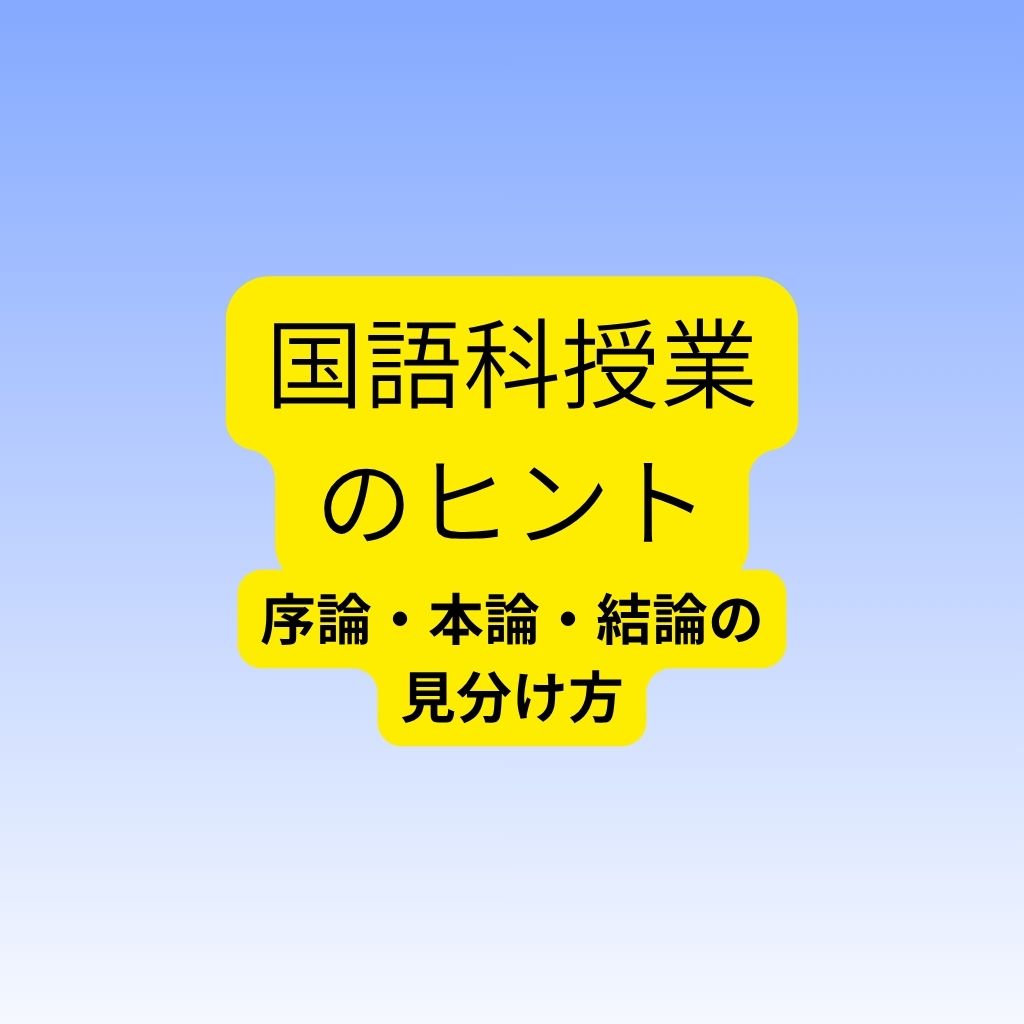


コメント