こんにちは、やまりです。涼しくなってきたこの時期、やたらと説明的な文章と論理の題材が増える印象があります。
思考力を使うのにいい季節だからでしょうか。そしてやたらと12月あたりに古文漢文関係の題材が多い気がします。
今回は、論理の話をするときに使いやすい、4枚カード問題をご紹介します。
4枚カード問題とは?
A K 2 13 と書かれた4枚のカードがあります。このとき、
・母音の裏には偶数が書かれている
ことを確かめるには最低何枚のカードをめくればいいか?また、どのカードをめくればいいか?
という問題です。ぜひ、ここでスクロールを止めてノーヒントでチャレンジしてみてください。
正解は A と 13 のカード
正解はAのカードと13のカードです。
なぜなら、母音の裏には偶数が書かれていることを確かめるためには
・Aの裏に奇数が書かれていないか
・13の裏に母音が書かれていないか
この二つを確かめればOKだからです。
逆に
・Kの裏に何が書かれているか
はこのルールには関係がありませんし、
・2の裏に母音が書かれていてもルール通り
であるため、わざわざ確かめる必要性がありません。
ですから、確かめるべきは
・Aの裏に奇数が書かれていないか
・13の裏に母音が書かれていないか
この二つを確かめればOKとなります。
論理学をかじっていると簡単
この問題、論理学をかじっていると簡単に解けます。
論理学でいうと、
AならばB が成立するとき、必ず
BでないならAではない(対偶)
が必ず成立します。
犬なら動物である
→ 動物でないなら犬ではない
といった感じです。
逆は必ずしも真ならず
対偶が成立するのに対して、論理学でいうところの 逆 と 裏 は必ずしも成立しません。
逆:動物なら犬である(猫のときもあるため成立しない)
裏:犬でないなら動物ではない(猫や鳥は動物)
といった感じですね。
これらの
・対偶は成立する
・逆は必ずしも真ならず
を知っていると、最初の4枚カード問題は簡単に解けます。
・偶数の裏は母音である
・母音でないカードの裏は奇数でない
ことを確かめればOKだとすぐにわかるためです。
具体的なものにするとすぐわかりやすくなる
これの事例を具体的なものにすると正解率が跳ね上がるそうです。
例えば
未成年はお酒を飲んでいない
というルールがあるとき
A:未成年で何か飲んでいる人
B:成年で何か飲んでいる人
C:ジュースを飲んでいる年齢不明の人
D:お酒を飲んでいる年齢不明の人
これなら、もっとわかりやすいのではないでしょうか。
確かめるべきは、Aの未成年の飲み物と、Dの酒飲みの年齢です。
これも
ルール(命題):未成年はお酒を飲んでいない
対偶:お酒を飲んでいる人は未成年ではない。
を確かめればいいのですから、これもAとDを確かめるのが正解となります。
今回の4枚カード問題と、論理学の「逆は必ずしも真ならず」などは、野谷茂樹先生の「論理学」という本で読んだ覚えがあります。
説明的な文章の読解を教えるにあたり、論理的思考とは?と色々読み漁った結果、この野谷茂樹先生のご著書が非常にあたりが多かったため覚えています。他にもそれゆけ!論理さんや、大人のための国語ゼミ、論理トレーニング101題なども、国語の論理的思考力を育成するのに非常に有効だと思います。
おそらく、AIvs教科書が読めない子供たちで紹介されているリーディングスキル(基礎的読解力)を鍛えるのに有効なんじゃないかなぁと個人的には思っています。
論理問題を自分の手を動かして解いてみる。よければぜひお試しください。
直接ではありませんが、私は生活の役にも立ちました。
自分は保険の対象に当てはまるのか、NISAで買える金融商品を何にするか、などなど場合分けをして当てはめて選択するケースは、生活のそこかしこに存在するためです。
それでは皆さん、明日も良い1日をお過ごしください。
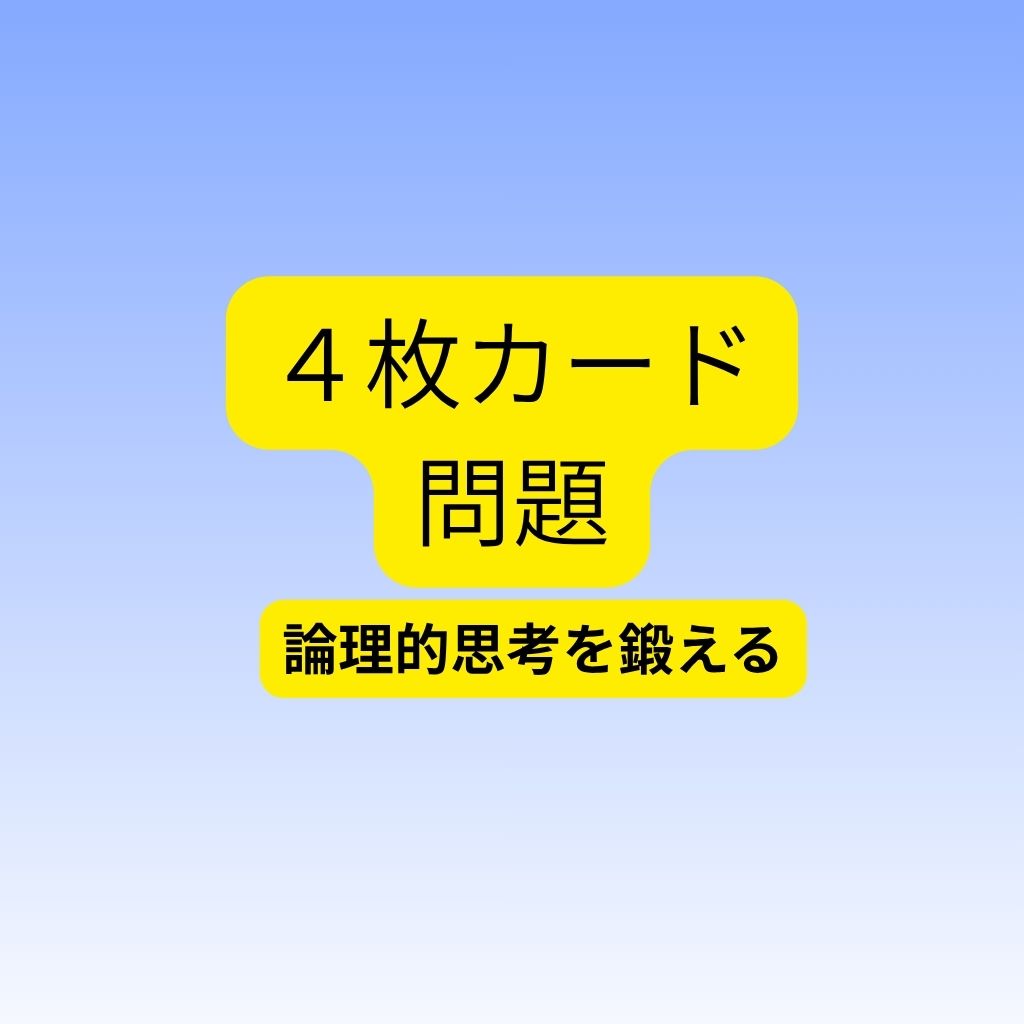


コメント