こんにちは!
学校でクラスのリーダーや生徒会長などの役職を担う子どもたちに、**「どうすればみんなにうまく指示が通るんだろう?」**と尋ねられたり、ご自身が指示を出す立場で悩んだりした経験はありませんか?
特に全校集会など大人数の場面で、指示の出し方に悩む先生やリーダーは多いものです。
今回は、集団を動かすリーダー的存在に対して、先生がすぐに使える、非常に強力なアドバイスを一つご紹介します。それが**「一時一事の法則」**です。
結論:「一時一事」で指示は確実に通る
指示は一つずつ、段階的に
「一時一事の法則」とは、**「一つの時に、一つの事だけを指示する」**ことです。
例えば、全体に指示を出す場合を考えてみましょう。
【悪い例】
「静かに並んで、点呼を取って、報告ができたら座ってください。」
(一度に5つの指示!)
これでは、聞いている子どもたちは「今、何を優先すればいいの?」と混乱し、確認のための私語が発生せざるを得ません。
【良い例】
- 「静かにしてください。」(全員が静かになるまで待つ)
- 「並んでください。」(全員が並ぶまで待つ)
- 「点呼を取ってください。」(点呼完了の報告を待つ)
- 「座ってください。」
このように、一つ前の指示が全体で完璧にできてから、次の指示を出すようにすると、驚くほど指示が通りやすくなります。
なぜ「一時一事」が効くのか?
集会や授業などの大人数の場面では、**「わかりやすさ」**が何よりも重要だからです。
一度に複数の指示を出すと、「今すぐやるべきこと」が曖昧になり、指示を聞いていない子も増えます。しかし、「静かにする」という一つのことだけに集中させることで、「今、自分は何をすべきか」が明確になり、みんなが同じ行動をとるようになります。
効果を最大化する**「待つ」**技術
進まないのは誰のせいか?を明確にする
「一時一事」で指示を出した後に、意外と重要なのが**「待つ」**ことです。
一つの指示を出した後、全員がその行動を完了するまでじっと待ちましょう。この「待ち」が、次の強力な効果を生みます。
それは、「先に進まないのは誰が原因か?」が、集団の中で明白になることです。
「無言の圧力」が状況を動かす
子どもは、先生の指示を無視することには慣れていても、**「集団の輪を乱している」と見られること、そして「自分一人のせいでみんなを待たせている」**という事態を極端に嫌がります。
- 例えば授業で「教科書15ページを開きなさい」と指示を出したとします。
- もし、内職をしている子がいるのにすぐに次の音読に進んでしまうと、「指示を聞かなくても授業は進む」と子どもたちは学習してしまいます。
一方、全員が教科書を開くまでじっと待った場合、内職をしている子は「授業が進まないのは、教科書を開いていない自分(誰か)のせいだ」と感じざるを得ません。友達からの無言のプレッシャーは、先生からの注意よりもよほど効く場合が多いのです。
これにより、指示を聞かなかった子も自ら行動を改めるようになります。
リーダーに「自分の影響力」を自覚させる
**「仲間からの指示」**は最強
この「一時一事の法則」と「待つ技術」は、指示を出すのが先生ではなく、同じ子どもであるリーダーの場合に、さらに効果を発揮します。
リーダーからの「静かにして」というシンプルな指示に対し、全員が動きを止めるまでリーダーが毅然と待つことで、以下のような心理的効果が生まれます。
- 反発の標的が分散する:先生の「命令」なら反発する子も、**「仲間のお願い」**を無下にして集団から危険視されることを恐れます。
- リーダーの自覚を促す:リーダーは**「大人にもない、自分自身の集団に対する影響力」**を自覚でき、自信をもってリーダーシップを発揮できるようになります。
だからこそ、この「一時一事の法則」をリーダータイプの子どもたちにそのままアドバイスする価値があるのです。
まとめ
一時一事の法則を意識し、一つひとつを確実に完了させてから次の指示を出すことで、集団への指示は格段に通るようになります。
- 一つの時に、一つの事だけを指示する。
- 全員が完了するまで「待つ」。
このシンプルなコツを活かして、子どもたちのリーダーシップ育成に役立ててみてください。
【元ネタ書籍のご紹介】
今回ご紹介した法則は、**『新版 子供を動かす法則 (学芸みらい教育新書 2) 向山洋一著』**からの知恵です。
この本には他にも、「やった後どうするか指示せよ」といった、一斉指導の際に役立つ具体的なコツが満載です。教育に携わる全ての方にとって非常に役に立つ「教師本」ですので、ご興味のある方はぜひ手に取ってみてください。
それでは、明日も良い一日をお過ごしください。
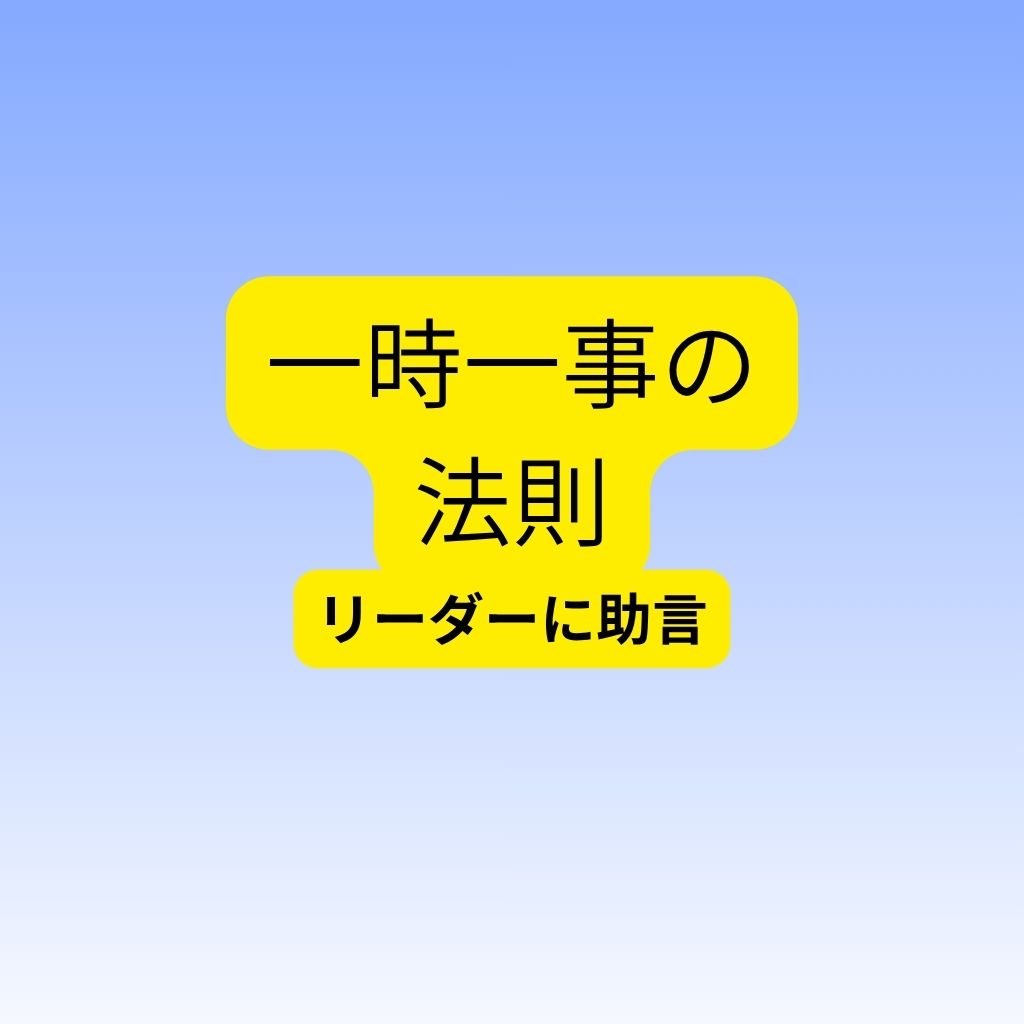

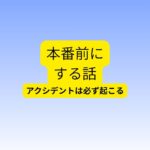
コメント